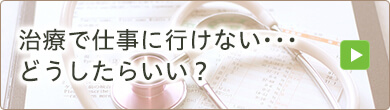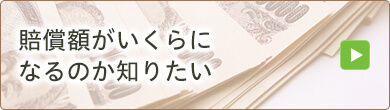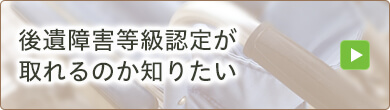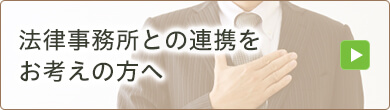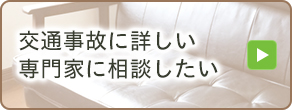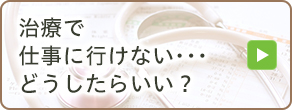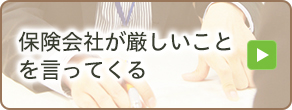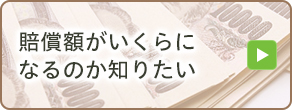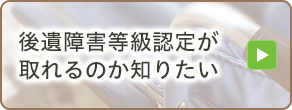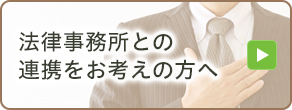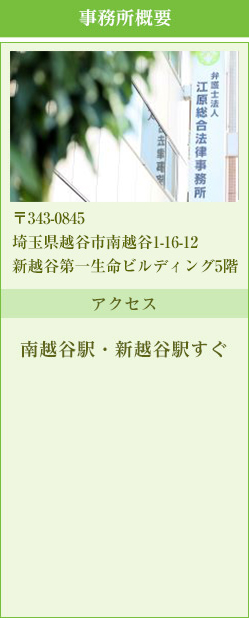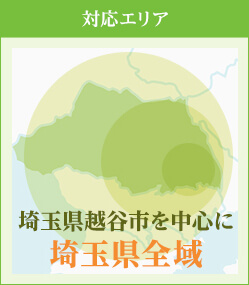高次脳機能障害

高次脳機能障害で苦しんでいる被害者とご家族へ
高次脳機能障害の難しさは、障害を残した被害者本人にその病識が無いところにあります。脳の障害ゆえに周囲に理解されにくいケースもあります。比較的短期間で退院するケースがあるため、その後の経過観察で高次脳機能障害が適切に評価されずに、そのまま放置されてしまうケースもあります。
当事務所が実際に経験した事例を一部ご紹介します。
なぜこれだけ高次脳機能障害という傷病が理解されないのか、仮に弁護士が関与しないままであればどうなってしまったのだろうと強い疑問を抱いた事案を複数経験しました。
・事故後の記憶力・認知力の低下が単なる老化による認知症の発症として扱われる
・特養に入所することになり、賠償においては何らフォローがなされないまま、投げ出された被害者
→当事務所介入後、併合6級の認定
・保険会社から後遺症がないと認定され(事前認定は非該当)
→当事務所介入後、後遺障害等級2等級を獲得
・性格の変化(感情のコントロールが困難になったことによる易怒性)が原因で入院先の主治医と感情的な対立を生じ、高次脳機能障害の認定もなく即時退院となったケース
→嗅覚障害のみ12等級の認定が、当事務所介入後、併合7級に繰り上げ認定

ご家族にとっては、被害を受けた方が事故の前の状態に戻ると信じリハビリをサポートすることになります。しかし完全には元に戻らないという状況、それが高次脳機能障害という後遺障害であるということを受け入れることにも大変な苦痛を伴います。当然ながら介護を伴う案件は適切な介護費用が補償されなければなりません。
当事務所は、このような高次脳機能障害の被害者、そのご家族と一緒に、あるべき被害回復の観点から最終的な賠償の獲得までサポートしたいと考えております。
高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは脳に外傷を受け、脳の高次機能をつかさどる組織が損傷し、障害が生じることです。
高次脳機能障害の症状は一見普通に見えても、交通事故の前と比べて記憶力や集中力が低下したり感情のコントロールができなくなって、他人と協調できなくなることがあります。
一見普通に見えるため、周りの人が気づきにくいことで対処が遅れることも多いので、少しでも可能性がある場合は、お早めにご相談ください。
高次脳機能障害を誘発しやすい傷病
高次脳機能障害を誘発しやすい傷病としては、以下などが挙げられます。
① 脳挫傷
② びまん性脳損傷・びまん性軸索損傷
③ 外傷性脳室出血
④ 急性硬膜下血腫
⑤ 外傷性くも膜下出血
① 脳挫傷
頭部に対する強い力が原因となり局所の脳組織が挫滅・砕けた状態(頭部の打撲状態)をいいます。症状としては、頭痛、嘔吐感、意識障害が認められます。衝撃を受けた部位の反対側にも損傷をきたすことがあるのが特徴です。
② びまん性脳損傷・びまん性軸索損傷
頭部に回転性の外力が加わることで、脳全体、または、脳の神経細胞の線維(これを軸索といいます)が広範囲にわたって断裂し、その機能を失ってしまうことをいいます。「びまん性」とは、病変がはっきりと限定されず広範囲にわたっていることをしめします。
びまん性軸索損傷・びまん性脳損傷では、受傷直後から意識失っていることが通常です。交通事故の被害にあわれ、病院に搬送され、受傷直後から6時間を超える意識障害が認められるとき、この傷病の診断がなされることが一般です。この傷病では、手術はほとんど効果がなく、通常、この傷病と診断されると、極めて深刻な後遺障害すなわち高次脳機能障害となることが予想されます。
③ 外傷性能室出血
脳の中心である脳室とよばれる空洞の部位に外傷が原因となって出血が生じた状態をいいます。脳室の内部は脳脊髄液で満たされており、その脳脊髄液はいくつかの脳室を順に流れていきますが、脳室内出血によって脳脊髄液の流れが滞ると、脳室が急速に拡大し、周囲の脳を圧迫します。徐々に流れが滞り、脳室が肥大化した場合は、正常圧水頭症と診断されます。脳挫傷などによって脳室の壁が損傷を受け、そこからの出血が脳室内に滞ることで脳室内出血を引き起こします。
受傷後の症状としては、激しい頭痛、嘔吐、意識障害などが認められ、一般には早急に手術が必要になります。
④ 急性硬膜下血腫
例えば交通事故などで頭部に衝撃が加わり、頭蓋骨の内側で硬膜(脳を包んでいる頭蓋骨の内面に張り付いている膜です。)と、脳の間に出血が溜まった状態をいいます。先に説明した脳挫傷の病変が発生した部位の対角線上にこの急性硬膜下血腫が認められることも少なくありません。症状としては激しい頭痛、嘔吐感、意識障害などが認められます。血腫による圧迫が進み脳ヘルニア状態になると、死に至ることもあるので注意が必要です。
⑤ 外傷性くも膜下血腫
脳を包んでいる髄膜(硬膜、くも膜、軟膜)の3層のうち、くも膜と脳の間の出血をくも膜下出血といいます。交通事故による外傷を原因とする場合、「外傷性」くも膜下出血と診断されています。先に述べた脳挫傷と併せて診断されることが多いです。症状としては、出血の範囲等によって異なりますが、激しい頭痛や嘔吐感が見られます。脳表部の部分的なくも膜下出血であれば予後は良好とされますが、広汎な出血がみられる場合や脳底部の出血となる場合は、深刻な後遺障害も予想されます。
なお、頭部外傷の傷病名のうち、急性硬膜外血腫にとどまり、幸いにも受傷後の意識障害がみられない場合、高次脳機能障害とならないことが多いです。脳と接する硬膜「下」血腫ではなく、脳を包む硬膜の「外」の血腫(そのため硬膜外血腫とよばれます)であり、脳への器質的損傷がないためと考えられます。
以上に述べたような傷病の診断を受けた場合、重篤な後遺障害(高次脳機能障害)になることが予想されます。
高次脳機能障害が予想される交通事故事案では、適切な知識と経験をもった弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所ではこれまで数多くの高次脳機能障害の案件を処理しておりますので、高次脳機能障害でお悩みの方・ご家族の皆様は、ぜひ一度お問合せください。
後遺障害の等級認定について
高次脳機能障害の場合には、以下のような基準で後遺障害の等級が認定されます。
| 等級 | 認定基準 |
| 1級1号(要介護) | 身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、 生活維持に必要な身の回り動作に全面的介助を要するもの |
| 2級1号(要介護) | 著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって1人で外出することができず、日常の生活範囲が自宅内に限定されている。 身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの |
| 3級3号 | 自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、 円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの |
| 5級2号 | 単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの |
| 7級4号 | 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの |
| 9級10号 | 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの |
後遺障害認定の要件
高次脳機能障害の認定においては、そもそも被害者に生じている症状が高次脳機能障害と評価できるか、高次脳機能障害と評価できるとしてどの等級に該当するか、が問題となります。
高次機能障害と認定できるか
まず、被害者に生じている症状(記憶障害、性格の変化等)が、高次脳機能障害として認定されるためには、一般的に以下の3つの要件が必要とされています。
② 頭部外傷を示す傷病名が診断されていること
③ ②の傷病名が画像で確認できること
上記①の意識障害とは、昏睡・半昏睡で開眼・応答しない状態(JCSが3~2桁、GCS12点以下)が少なくとも6時間以上継続することをいい、健忘症・軽度の意識障害とは、JCSが1桁、GCSが13~14点が少なくとも1週間以上継続していることをいいます。意識障害は、高次脳機能障害の認定を受けるための入口の要件であるとともに、意識障害の程度や継続期間が、後遺障害として認定される等級の判断にも影響します。そのため、事故直後に意識障害の症例が見受けられる場合には、脳外科医の先生に適切な検査をしていただくことが重要です。
上記②の頭部外傷を示す傷病例としては、脳挫傷、びまん性軸索損傷、びまん性脳損傷、外傷性脳室出血、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、低酸素脳症などが挙げられます。
なお、上記①~③の事情がすべて満たされていなければ、高次脳機能障害の認定を受けることができないわけではありませんが、いずれかの要件を欠く場合には、高次脳機能障害の認定を受けることは極めて困難か、軽度の等級の認定にとどまるのが通常です。
どの等級に該当するか
次に、現実に被害者に生じている症状の程度に応じて、被害者の高次脳機能障害がどの等級に該当するかが判断されます。
高次脳機能障害として認定され得る等級は、1級、2級、3級、5級、7級、9級、12級、14級と幅広く、どの等級に該当するかによって賠償額が大きく異なります。各等級における抽象的な認定基準は、以下の通りです。
① 1級1号 高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身の回りの処理動作について、常に他人の介護を要するもの
② 2級2号 高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身の回りの処理動作について、随時介護を要するもの
③ 3級3号 生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの
④ 5級2号 高次脳機能障害のため、極めて軽易な労務のほか、服することができないもの
⑤ 7級4号 高次脳機能障害のため、軽易な労務しか服することができないもの
⑥ 9級10号 通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
⑦ 12級13号 通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の傷害を残すもの
⑧ 14級9号 通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの
被害者の症状が、上記①~⑧のどの等級に該当するかは、事故直後の意識障害の程度・時間、傷病名、症状固定時の症状(記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会行動障害、病識欠如など)の程度に応じて、判断されることになります。
上記の認定基準からもお分かりになると思いますが、高次脳機能障害の認定は、非常に微妙な判断を含みます。そのため、高次脳機能障害が疑われる症状でお悩みの方やそのご家族は、お早めに専門的な知識や経験を有する弁護士に相談することをお勧めします。
高次脳機能障害の際に併発しやすい後遺障害

交通事故により頭部に衝撃が加わり脳に損傷を負った場合、高次脳機能障害と併発して両手両足の麻痺、視力・聴力障害、嗅覚味覚の障害や、頭痛・めまい等の重篤な症状が発症することがあります。
交通事故が原因で脳を損傷したことに伴い麻痺などの身体性機能障害、てんかん症状、頭痛、めまい等の平衡機能障害、うつ等の比器質性精神障害が残った場合には「神経系統の機能障害」として症状の程度に応じて、後遺障害等級が認定されます。
脳を損傷するような交通事故では、眼や耳、鼻に障害が残ることも多いです。このような場合にもそれぞれ単独で後遺障害等級が認定されます。このうち、眼の障害は(1)視力に関する障害、(2)眼の調整機能に関する障害、(3)眼球の運動機能に関する障害、(4)視野に関する障害、(5)まぶたの欠損に関する障害、(6)まぶたの運動に関する障害に分類されます。また、耳の障害には、聴力障害や、耳鳴り・耳漏が残る障害が、鼻の障害には、欠損を伴う機能障害(嗅覚の脱失・減退や呼吸困難)と、欠損を伴わない機能障害があります。
味覚に障害が残ったような場合にも、等級表には記載がありませんが12級または14級の後遺障害等級が認められています。
上記に加えて、交通事故の衝撃により頭部や顔面に傷跡が残ってしまったような場合には「外貌の醜状障害」として後遺障害等級が認定される可能性があります。
その他、高次脳がクローズアップされてその他の身体に対する傷害に起因する後遺症(関節の機能障害等)が見落とされることもあり、嚥下障害等、見落とされやすい後遺障害が発生したケースも経験しています。
高次脳機能障害を伴うような交通事故に遭った場合、脳やその周辺部分の損傷を原因として他の後遺障害を併発するケースが多く、その他の症状も見落とされる可能性があるため、等級認定の際に他の症状が見落とされてしまうことがあります。お早めに交通事故に精通した弁護士に相談し、検査や診断の見落としがないかどうか、事案に応じて検討する必要があるでしょう。
高次脳機能障害の認定のポイント
高次脳機能障害は目に見えないため、後遺障害の中でも認定が難しいものの1つです。裁判になる場合に備えて予め弁護士等の専門家に相談し、十分な資料を準備しておくことをお勧めいたします。
以下には、裁判を見据えて、後遺障害として認定されるためのポイントを記載致しますので、参考にしてください。
① 専門の医師に受診する
脳神経外科、整形外科だけでなく、神経心理学、リハビリテーションにも精通した専門の病院で診断を受ける必要があります。
② 画像を撮影する
高次脳機能障害の症状が現れた場合には、すぐにMRIの撮影を依頼してください。事故から時間が経てば経つほど、異常を発見するのが難しくなります。
③ 神経心理学的検査をする
脳の機能には、知能、言語、記憶力などがあり、どの機能の検査かによって、実施する検査が異なります。知能の検査が必要な場合には、WAIS-R、長谷川式簡易痴呆スケールがよく用いられ、記憶力の検査が必要な場合には、WMS-R、三宅式記銘検査などがよく用いられます。
④ リハビリに通う
リハビリに通っていなければ、高次脳機能障害であることを示す客観的な資料が残りません。定期的にリハビリに通うことが大切です。
⑤ 後遺障害診断書を作成してもらう
リハビリに通うことは大切ですが、リハビリにも限界があり、その効果をあまり発揮しない時期が訪れます。この場合、後遺障害が残ったことになるので、適切な時期に後遺障害として診断してもらう必要があります。
もちろん、後遺障害診断書は後遺障害を認定してもらうために適切に作成してもらう必要があり、また、神経系統の障害に関する医学的意見、日常生活状況報告といった重要な書類を作成する必要があります。
高次脳機能障害と認定された場合の賠償額
高次脳機能障害と認定された場合に支払われる損害項目としては、代表的なものを挙げると、次のようなものがあります。
⑴ 治療関係費用
まず、治療費や入院費などの治療関係費については、必要性や相当性に問題がある例外的な場合を除き、その実費全額の賠償を受けられます(被害者側の過失がないことが前提です。)。また、症状が重篤な場合には、通院付添費や将来介護費、その他ホームヘルパーの費用などの介護関係費用、家屋や自動車の改造費用等も損害として認められる可能性があります。
⑵ 休業損害・逸失利益
休業損害は、事故による負傷や治療のため、本来得られたはずの収入が得られなくなったことによる損害、逸失利益は、後遺障害により、将来得られたはずの収入が得られなくなったことによる損害をいいます。
年齢や職業によって、賠償額は異なりますが、例えば、事故時29歳(症状固定時31歳)であった男性が、事故による高次脳機能障害、嗅覚脱失、味覚減退等により併合4級の後遺障害と認定された事案において、就労可能な67歳までの逸失利益として、約8600万円を損害として認めた裁判例があります。
このように休業損害や逸失利益は、事故後の被害者やその家族の生活を保障するものであることから、賠償額は高額になる傾向があります。
⑶ 慰謝料
慰謝料については、過去の裁判等の蓄積により、ある程度の基準が形成されており、入院や通院を余儀なくされたことによる慰謝料(入通院慰謝料)と、後遺障害が残ってしまったことに伴う慰謝料(後遺障害慰謝料)の2つに分けられます。
入通院慰謝料は、原則として入通院期間を基準として、損害額を算定します。例えば、事故により2カ月間入院し、その後8カ月間通院を余儀なくされた場合、入通院慰謝料は194万円が基準の金額となります。
他方、後遺障害慰謝料は、後遺障害として認定された場合の等級を基準として、損害額を算定します。高次脳機能障害が後遺障害として認定された場合、原則的には、9級以上の等級がつきますが(12等級や、他覚的な所見が無い場合には14等級にとどまるケースもあります。)、例えば、後遺障害が9級と認定された場合の後遺症慰謝料は690万円、5級と認定された場合の後遺症慰謝料は1400万円、1級と認定された場合の後遺症慰謝料は2800万円が、それぞれ基準の金額となります。
以上のように、高次脳機能障害と認定された場合の賠償額は高額になる傾向があります。
もっとも、はじめから相手方の保険会社が上記のような金額を損害として認めてくれるわけではなく、相手方は、なるべく支払額を抑えようとしてきます。適切な賠償額を得るためには、何が損害として認められるか、相手方に対してどのように説得的に伝えるか、損害の発生をどのように立証するかが重要であり、そのため、高次脳機能障害が後遺障害と認定された後の、最終的な損害額の算定に当たっても、法律の専門家である弁護士の介入が不可欠といえます。
![]() この記事を書いた人
この記事を書いた人

弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。
お困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
メールでのお問い合わせ
24時間受付